京都観光 おすすめ 京都の芸術 歌道
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 歌道 平安時代
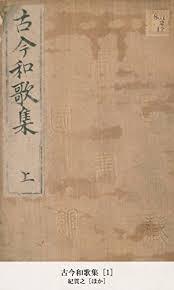
京都の歌道は905年に紀貫之が醍醐天皇に奏上した我が国最初の勅選和歌集「古今和歌集」に始まります。「やまとうたは、ひとのこころをたねとして、よろずのことのはとぞなりけり」という仮名序の宣言は一貫した歌の心として現代に至るまで面々と受け継がれています。紀貫之の同時代の歌人には六歌仙の遍照・在原業平・文屋康秀・喜撰・小野小町・大友黒主や紀友則・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)・壬生忠峯が有名です
勅撰和歌集のうち最初の最初の八集である「古今和歌集」「五撰和歌集」「拾遺和歌集」「後拾遺和歌集」「金葉和歌集」「詞花和歌集」「千載和歌集」「新古今和歌集」を八代集とよびます。この間、優れた女流歌人が次々と生まれました。小野小町と双璧を成すと言われた伊勢、数々の名歌で知られる和泉式部、紫式部と親交のあった赤染衛門が有名です。名歌に詠まれた名所が歌枕として定着するようになりました。「化野」「嵐山」「大堰川」「鳥辺山」「深草」「小倉山」が代表的です。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 歌道 鎌倉時代

鎌倉時代の和歌は、出家の西行と藤原俊成の「幽玄体」に始まり、藤原定家の「有心体」に至って和歌史の頂点を極めることになります。藤原定家は晩年には古代以来の秀歌を集めた「小倉百人一首」の撰を手がけました。藤原定家の御子左家は孫の代に、歌の家として二条家、京極家、冷泉家に分かれて中世の歌壇の指導にあたりました。
冷泉家は藤原定家の孫の為助を祖とする800年の歴史を持つ「和歌の家」です。現当主為人氏は25代で、月並歌会をはじめ王朝以来の伝統行事を現在に伝えています。冷泉家住宅(重要文化財)は上京区今出川通烏丸東入にあって近世中級公家邸の唯一の遺構です。月次歌会をはじめ乞巧纏(きっこうてん)など王朝以来の貴重な行事を現代に伝えています。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 歌道 近世

近世の和歌は、古今伝授を伝える細川幽齋や、豊臣秀吉室の甥木下長囃子、京都の平安四天王一人小沢魯庵、桂園派の中心香川景樹、女流の太田垣連月が有名です。
明治以降は短歌中心となり、京都との関係でいくと与謝野鉄幹・晶子、山川登美子、吉井勇が有名です。
関連する投稿
- 京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 花街のしきたり Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の行事 Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史② Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史① Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 京舞と井上流 Kyoto Art Kyomai(Kyoto Dance)
現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の芸術 歌道






